美術評論家
闇という光に映る風景 ― 鮮やかな心の宇宙
武田 厚(美術評論家)
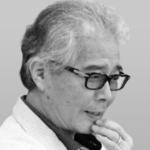
初めて見るパトリック・ジェロラの作品に初めて知る快感を得た。つまり味わったことのない初体験といえる種類の快感ということである。その実感を率直に言葉にすると、まずその色彩の鮮やかさと強さである。しかし強烈ではあるがしっとりとした艶のある落ち着きで目を 癒してくれる不思議な色感なのである。次にストロークに見る美観。作品のすべてではなが、伸びやかな腕の動きが時に軽やかに、時に重厚に空間を跳ねる様子見ていて理屈なく気持ちのいいものである。そして 3 つ目は画面にちょされたミステリアスな世界のことだ。私が関心を持った以上のこともう少し詳しく観察してみようと思うが、その前に画家としての彼の履を概観する必要があるだろう。
パトリック・ジェロラはベルギー、ブリュッセルの生まれで、1983年、24 歳の時に来日し、以来日本が生活の場となり作家活動の場となっている。無論、来日間もなく出会って結ばれた声楽家の夫人の支えがそこにあったことを先に記しておく。その彼は画家といっても絵だけ描いているわけではない。彫刻等の立体造形、グラフィカルな仕事、装飾美術、インスタレーションなど絵画以外のものにも成り行きに順応して積極的に関わってきた。しかしながら、どちらかといえば画家、と自身は述べている。発表活動の場所はベースとなる日本以外へも徐々に拡張し、その個性的な感性に関心を示す層の広がりが認められるようになる。
年譜にもある通り、母は画家で兄も画家を志していた。しかし美しかった母は彼が子供のころに亡くなった。兄は永くイタリアに在って、今も画家として活躍している。彼はそうした環境の中で自ずと美術というものに親しく接して育った。ブリュッセルの王立美術アカデミーで学んだ後、81 年からほぼ 2 年あまり舞台美術の仕事に関わる。日本でもよく知られるモーリス・ベ ジャールの舞踊学校で芸術監督を務めていた振付師のもとでのその仕事は、後に画家として活動する彼にとって極めて有益で実り多いものだったと想像される。色彩、空間、ムーヴマン、構成等に関する感性が無意識的に磨かれ、演出性に関する意識の高まりなどもあったのではないかと思う。平面でも立体でも、彼の作品作りの発想は常に三次元的であり、その発想の底辺には絶えず第三者の目と心があり、そのために展開される作品と作品の 置かれる空間がいかにあるべきか、を妥協することなく探し求める姿勢があるように私は感じた。彼が美術における演出の重要性に関心を抱き、それを自身の仕事の上で実践してきたのは、まさに舞台美術の体験が大きく影響している、と私は感じたのである。
ところで、冒頭に書いた 3つの特色についてだが、先ず鮮やかな色彩の発生については、それは自製の色素材によるものであることが分かった。フレスコ画の技法から独自に発案したものらしく、顔料に樹脂を加えて混ぜ合わせた新絵具である。カンヴァスに載せられたそれらの色は艶のある伸びやかな色感を見せ、何故かイタリアンデザインの色をも感じさせると私は思った。加えて制作時における照度のコントロールのこともある。例えば白日のようなフラットな明るさの中でうまれる色の彩度には満足しないし疑問も抱いている。彼は敢えて照度を落とすことで浮かぶ立体的な光の効果を感知し、そうした環境の下で制作することによって、画面を支配する独特の鮮度を保った色彩を産み出しているのだ。つまり、私流に言えば、“ 闇という光 ” に映る魔法の色。
ストロークの美観については、前にも書いたが、恐らくはモダンダンスに関わる仕事で体感した身体的な躍動感に対する感動が反映されているように私は思った。三次元の空間を自由に美的に動く感覚がそのまま平面の上でもリズミカルに躍動できているように感じるからである。ダンスとしてのストロークが鮮やかで明快な色面と相まって画面を生きき生きとした舞台に仕立て上げている。
3 つ目のミステリアスな世界のことだが、これは画面をじっと見ていると恐らく誰もが体験することではないかと思う。初めは実に平面的でグラフィカルな手法であることを理解するのであるが、少し時間が経つと、非現実的な風景であるにも関わらず、目と心が画面の向こうへ、つまり見たこともない風景の向こうへ、と誘われる 気がするのである。まったく味わいのないベタ塗りの空、それとは対照的に賑やかな花々に埋まる丘陵の傾斜する姿、貼り絵のような平たいだけの木々の隙間に覗く本当のような景色などなど。これらの大胆で率直で素朴 な表現は極めて個別的なものだと思っているが、同時に、その画面から感じさせられるちょっとしたミステリアスな空気は、確かに、ベルギー生まれの先達、例えば 誰でも知っているマグリットやデルヴォーの作品の世界に底流するお洒落なサプライズとユーモアを楽しむ精神にどこかで通じているのかもしれない。そこが彼の作品を愛する人たちにとってはもう 1 つの魅力となってい るような気がする。
パトリック・ジェロラは、感じたもの、閃いたもののすべてをキャッチして離さない。日々の生活の中で見る 色も聞く音もすべてを自身の体内に吸収していく。身近な自然のすべてが彼の作品の誕生の素になる。日本に住んで日本の伝統や風物に感動することは無論少なくない。その閃き、つまりジェロラという作家の感性に響いて生まれた想いがそのまま線となり色となり形となっているようだ。故国の文化も同じことだ。日本人なら誰でも知っているブリュッセルにある小さな小便小僧が、日本で 2 メートルを超す巨大な小便小僧に生まれ変わっている。無論彼のオブジェである。しかも巨大小便小僧たちはいずれもジェロラの絵を全身に纏って第二の人生を生きつつある。日本で生まれた絵である。ベルギーと日本との文化交流の自然な形である。
再び “ 光 ” のことだが、彼は自身の仕事において最も意識するのは “ 光 ” のように思う、と述べている。画面の中の心象的な風景に見る心象的な光もその一つであろう。ベルギーといえばピーテル・ブリューゲルがいい、と彼は言う。ブリューゲルの絵画の世界を求めて現地を探し訪ねたこともあるようだ。ブリューゲルの世界の光も魅力的だが、私の場合は初めてブリュッセルを訪ねた 時の街の光が強く印象に残っている。光というよりも灯りである。夜遅くに空港からの車で街に入った時に見た点々とした赤色街灯の景色だった。その幻想的な光の中に漂うその国の風土やミステリアスな画家たちのことを何故かその時直感したのだ。だから今回も、そうした私 だけのベルギーの光というものを通してジェロラの絵を見ているかもしれない。
東京, 2016年6月